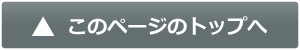専門教育とは、「〇〇〇」である!
ニュースレター45号より始まった「専門教育とは、「〇〇〇」である!」は、実践者・研究者、各々の立場で「専門教育」について考えるきっかけとなれば…という思いより、スタートしました。
若手研究者や現場の実践者を中心に、その人自身が考える「専門教育」とは何であるのかを「〇〇〇」という一言で表現してもらい、その理由(何を以て専門教育としているのかなど)などを教えていただく内容です。
第3回目は、小渡加依会員(特別養護老人ホームせんだんの館)、宮本雅央会員(北海道医療大学)の熱い想いをお届けします。
専門教育とは、「理想の専門職像を目指した土壌づくり」である!
小渡 加依(特別養護老人ホームせんだんの館)
はじめに
私は、介護職員を経て、特別養護老人ホームの生活相談員として勤務しております。2021年には社会福祉士養成・新カリキュラムが改訂され、多様化・複雑化する人々の生きにくさに対して、ミクロ・メゾ・マクロレベルの連続性によるソーシャルワークの実践が求められると知り、自らの知識不足と実践力に限界を感じたことを機に、2024年に東北福祉大学 大学院(修士課程)に入学をしました。働きながら専門教育を学び直している立場にいます。今の私が考える「専門教育」とは何か、一考察として私見を述べさせていただきます。
専門職としての土壌づくり

時代の変化に応じて、ソーシャルワーク専門職のグローバル定義や日本社会福祉士会の倫理綱領・行動規範が改定され、社会福祉士養成カリキュラム、各種の施策や制度も改正を繰り返してきました。その時代ごとの理念の実現を目指して、必要な専門教育を学ぶことが必要不可欠だと思います。一方で、専門教育を受けただけで専門職になれる訳でもありません。専門教育とは、専門性を構成する「価値・知識・技術」という土壌づくりを繰り返す工程であり、専門職であり続けるための学びを導く機会だと思います。
学部時代は「講義―演習―実習」のカリキュラムやボランティア活動などを通じて、学生それぞれが抱く「こういう社会福祉士(ソーシャルワーカー)になりたい」という理想像を構築しながら、専門職としての土壌(価値・知識・技術)の基礎をつくる大切な時期だと思います。卒業後、自らが関わるフィールドや、求められる役割・機能に応じて、専門分野や関連分野に関する専門教育を学び続けることで、土壌をより深く、より広く、より豊かに肥やすこと。その積み重ねが、自らが理想とする社会福祉士像に近づく道のりであり、専門職であり続けることができるのではないでしょうか。私の場合、大学院での学びが大きな刺激となり、仕事や私生活での出来事に対する見え方が変化し、それらが多くの肥料となり、新鮮な空気となって土壌の循環が活性化されていると実感しています。
あたりまえを疑い、「問い」続ける感性
先日、退官を迎える恩師の最終講義を拝聴する機会に恵まれました。恩師は世の中の不条理や理不尽な状況下で懸命に生きている人々に焦点をあて、歴史的な背景や変遷から社会福祉学のあり方を「問い」続けてこられました。孔子の論語(為政第二15)に、『学びて思わざれば則ち罔(くら)し、思いて学ばざれば則ち殆(あやう)し』という言葉があります。真にあるべき理想の学び方について、先人の知恵・教えを学ぶだけではなく、自ら考えて思案を巡らせなければ道理を理解できない。一方で、思案するばかりで学ばなければ考えが狭くなり、独断的になりやすいこと説いた言葉です。世の中のあたりまえ、専門職のあたりまえ、自分のあたりまえを疑い、それらが真にどのような意味や価値があるのかを「問い」直す感性を磨くことが、専門職の土壌をより豊かにすると思います。
おわりに
社会福祉士として、人々が生活する営みに脈々と受け継がれてきた普遍的なもののあり方を追い求めるためには、多くの人たちの考えや生き方に触れて、自ら学び、自ら考えることで「問い」への感性を磨くことが、専門職であり続けるために必要なのだと思案しました。また、自分と向き合い、人と向き合い、社会と向き合うための豊かな土壌づくりを育み、専門職であり続けるための学びを導く力が専門教育にあると思います。
最後に、このたびは「専門教育とは何か」について考える貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。至らない部分を含めて、今後も専門教育について考えてまいります。
専門教育とは、「枠を超える力を育むこと」である!
宮本 雅央(北海道医療大学)
専門教育とは,多様な社会課題に柔軟に対応し,新たな解決策を創出する能力を養成すること,そして新たな価値を生み出せる能力を習得することが重要であると考えます。簡潔に言い換えるならば,「既存の枠を超える力を育む」教育です。ここで述べた能力は,一般的な高等教育で掲げられる包括的な目標の一つであり,必ずしも社会福祉の専門教育に特有のものではないと捉えられるかもしれません。しかしながら,私は特に社会福祉の専門教育においてこそ,この能力を重視した取り組みを展開する意義が大いにあると考えています。
近年の「複雑化」しているといわれる地域生活課題への対応には,福祉・医療・教育・経済といった異なる分野を横断する視点が求められます。そして,この視点に基づいた実践には,地域にいる様々な人同士の協働(コラボレーション)が必要であり,そのコラボを実現するための仕掛け役が重要です。
このコラボに必要な要素には,ソリューション(課題解決)とイノベーション(新機軸,革新)が挙げられます。どちらも,今ある条件の中でより高い価値を生み出せるようデザインするという思考が含まれます。イノベーションは語源を辿ると「新機軸から捉えなおす」とか,「新結合を作り直す」というニュアンスがあり,「技術革新」よりも「捉え直し」が分かりやすい概念だと思います。そして,捉え直しデザインする思考の必要性は,現代的に急に現れたわけではなく社会事業家であるJ. アダムズの実践(木原 1998)の経過にも垣間見えると思います。そもそも,何を成すかという航海図に“その地域の人たちの暮らしの向上”があって,それを“みんなで成し遂げる”ために先人たちがコラボしてきた歴史を私たちは知っています。そして,現代的に必要なコラボを“誰がどのように仕掛けるのか”という問いに対して,社会福祉専門職が福祉という視座から登場すればいいと考えています。

専門教育では,単に既存の方法を学ぶだけでなく,新たな発想やアプローチを取り入れる力を培います。例えば,ICT(情報通信技術)を活用した福祉サービスの開発,地域の資源を活かしたコミュニティ支援のモデル構築などが挙げられます。学生たちは,こうした新しい取り組みを認識する中で彼らが置かれている社会の変化に適応しながら,持続可能な対人援助や福祉サービスのあり方を実現する方法を考案できます。さらに,先鋭的な取り組みの例と共に,その根底にある思想や哲学を同時に獲得できることは,教育関係者が提供する専門教育のあるべき姿の一つといえます。したがって,専門教育とは現状の枠の中で取り組めることと併せて,今は実現が難しい・新しいアイディアを学びつつ,その限界を認識し乗り越えるための思考を獲得する過程といえるでしょう。その中で学生たちに培われる思考が「枠を超える力」であり,その必要性を実感したり,アイディアの実効性や達成感を得られたりできるプログラムが必要であると思います。
さて,“その地域の人たちの暮らしを豊かにしたい”という願いは社会福祉専門職の専売特許ではなく,誰でも共有できる価値観だと思います。しかしながら,現代の社会システムにおける様々な状況の中で,何かの取り組みの目的や方法が合わないという複雑さがあります。ただし,入り組んだ仕組みの中で解決策を考えなければいけない状況自体は,最善を考え続けたり乗り越えるアイディアを形にし続けたりする誘因になっており,前向きに捉えられるとも思います。そして,複雑さがある中でも現状を改善していくという,人と人同士のコラボの発生源になっているともいえます。
様々な思想の人たちがバランスを取れる状況を作るためには,リスクコミュニケーション(経済産業省)に代表される,お互いの歩み寄りと相互の枠組みを理解しながら乗り越える過程(竹端 2012)が必要であると思います。それらを実現するための能力とは,“その人・状況に寄り添う”という対人援助の根本的姿勢が基盤にあります。そのため,もともと別の方向を向いているステークホルダー同士に社会的意義を踏まえて対話を促す仕掛け役には,その対象範囲に限界はないとされる(秋山 2007)人道的な感受性を持った社会福祉専門職が合うだろうと思います。
新たな価値を生み出す対話を実現するための社会福祉の専門教育は,固定された枠組みの中で知識を学ぶものではなく,多様な分野を横断し,新たな価値を創造することが求められます。そのためには,課題解決のための創造力,柔軟な思考,実践的な経験が不可欠です。こうした教育を通じて,社会の変化に対応しながら,人々の生活の質を向上させる新たな福祉の形を生み出していくことが可能になると思います。
参考文献
木原活信. (1998). “ジェーン・アダムズ -シリーズ福祉に生きる”. 大空社.
経済産業省. リスクコミュニケーション(METI/経済産業省). https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/risk-com/r_index2.html#MainContentsArea.
竹端寛. (2012). “枠組み外しの旅-「個性化」が変える福祉社会”. 青灯社.
秋山智久. (2007). “社会福祉専門職の研究“. ミネルヴァ書房.