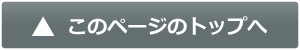アポリア連載
ニュースレター45号より、「アポリア連載」が始まりました。
「アポリア連載」は、会員の皆さまが、本学会の研究対象は「高等教育における社会福祉専門教育」という認識のもと、さまざまな高等教育機関から社会福祉教育のあり方を考えるきっかけとなれば、という想いより本連載を始めました。
第3回目は、本学会理事である阪口春彦会員(龍谷大学短期大学部)です。
「短期大学教育を考える」
日本社会福祉教育学会 理事 阪口 春彦(龍谷大学短期大学部)
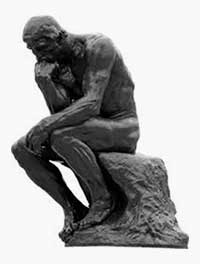
学校教育法第83条において、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」と規定されているのに対し、同法第108条において、「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的」とし、修業年限を2年または3年とする大学を短期大学と称すると規定されている。つまり、短期大学は、学校教育法において大学の制度の枠内に置かれたものと位置づけられ、学校種としては大学の一類型とされているということであり、短期大学とそれ以外の大学との違いにはその目的と修業年限があるということである。
ここで問われるべきこととして、「深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成する」という目的を達成することが、2~3年間の教育で十分なのかということがある。社会福祉教育においては、社会福祉士等の専門職の養成教育が2~3年間で十分なのかということである。
たとえば社会福祉士については、卒業後に1~2年以上の実務経験が必要であるが、短期大学も社会福祉士国家試験の受験資格を得ることができるルートの一つとして位置づけられている。しかしながら、社会福祉士の専門性の高度化が求められている現在においては、2~3年間の社会福祉士養成教育は困難であるとの声も聞かれる。とくに、社会福祉士の新養成カリキュラムにおいて、実習時間が180時間以上から240時間以上に変更となったことにより、学生が課外活動などに充てられる時間が短くなってしまっている。課外活動などをとおしての学びも重要であり、4年制大学と比べ短期大学の学生にとっては相対的にその影響は大きい。また、高校卒業後1~2年目で実習を行うケースが多く、社会経験等の不足から実習の実施に不安を感じる場合もある。しかしながら、社会福祉士の専門職として立派に活躍している短期大学の卒業生も多い。短期大学で指定科目を学び、卒業後に実務経験を積むことによってより実践能力の高い社会福祉士になれる可能性もあると言える。
また、短期大学とそれ以外の大学とでは、卒業後の進路にも違いがある。具体的に言うと、短期大学の卒業後の進路には、4年制大学等への編入学がある。筆者が所属している龍谷大学短期大学部は、4年制の総合大学に併設されていることもあり併設大学への編入学希望学生が非常に多く、編入学先の学部・学科等もさまざまであり、多様な進路の希望を持つ学生に対してどのような教育を行うのかは難問である。本学の場合、「編入学準備プログラム」を設けるなどして、さまざまな学部・学科等に編入学する学生への対応を行っている。社会福祉系以外の学部・学科等への編入学を希望する学生には、社会福祉に興味を持とうとしない者もいるが、社会福祉学は学際的であり、社会福祉はどのような学問とも何らかの関係はあるため、短期大学において社会福祉についてしっかりと学んでもらうとともに、編入学後の学習に備えるために希望する学問分野についても学ぶ機会を提供すること、そして社会福祉と希望する学問分野とのつながりに気付かせることが重要であると考える。
もう一つ重要なことは、入学定員を満たしておらず入試の選抜機能が十分に働いていない短期大学が多ということである。選抜機能が十分に働いていない場合、短期大学士にふさわしい力を身に付けて卒業できるようにすることは容易ではないが、入学生として受け入れた以上、リメディアル教育をはじめ、分かりやすく興味を持ちやすい教育内容・教育方法の導入など、さまざまな教育的対応を行い、短期大学士にふさわしい力を身に付けて卒業できるように努めることが必要である。
とくに社会福祉系の学科等については、入学定員の確保がより困難になっているため、社会福祉系の学科等を擁する短期大学が減少し、短期大学における社会福祉教育のあり方を考え学び合う機会が減少しているように思われるが、短期大学における社会福祉教育を行う教員等が、上記のような課題にどのように対応すべきなのか、本学会などをとおして考え学び合うことが重要であると言えよう。