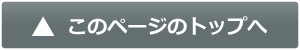巻頭言
社会福祉教育におけるコミュニケーション
日本社会福祉教育学会 理事 工藤 英明(青森県立保健大学)

巻頭にあたり、日々の教育実践を振り返り、教育とコミュニケーションについて若干の私見を述べてみたい。
現在の社会福祉教育は、資格養成カリキュラムに示されている制度・政策系と支援方法系科目に大別される。さらに、教授方法は、講義系科目と演習・実習系科目に大別される。講義系科目は、多数の学生を対象に知識の伝達や解説が中心となり、双方向・参加型を意識しても、一方向的コミュニケーションに近い。理解度の把握は、リアクションやレポート、テストを通して把握することになる。他方、演習系科目は、スキルの獲得や知識応用など実践的・知的トレーニングとして、双方向的で相互・交互作用を用いたコミュニケーションが可能であり、スキル獲得の程度の把握は、実技試験的も可能となる。実習では、指導者の指導や観察により経験知や暗黙知の獲得も期待される。しかし、これらは伝える側と受け取る側双方ともに意識的なコミュニケーションではない場合が多く、学生の学びに大きな差が生じていると感じる。具体的には、指導者は上手く言語化できないながらも、高度な実践を行っている。一方の学生は、それらを意識的に観察していない場合、見逃すこともあり得る。
近年、教育場面でのコミュニケーション方法は、旧来の対面での講義、配布される活字媒体資料に留まらず、ICTや動画、各種デバイス、VR教材の活用も広く導入されている。また、リモート、オンデマンド、クラウドやSNSを用いたレポート添削もできる。オンデマンドやSNSによる教育は、時差を有するコミュニケーションであり、オンデマンドは一方的、SNSは活字による添削となる為、ニュアンスや相手に合わせて伝えるための細やかな工夫や言葉が必要となる。新たな教育手法や教材が開発、進化しても、多様なコミュニケーション素材をさらに工夫する必要がある。
近年、学生個々の特性は多様化しており、教育場面でのSW的コミュニケーションも求められている。所属機関の大学院教育では、教育の質の担保からポートフォリオが導入され、教員と院生間の指導経過のコミュニケーションの見える化も図られている。教育とコミュニケーションは形を変えても切り離せない重要な要素である。
最後に、自身の臨床及び教育場面での人材育成に関する座右の銘を紹介して終える。「してみせて、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、人は動かじ」(諸説あり/上杉鷹山・山本五十六)。